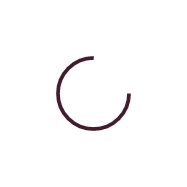
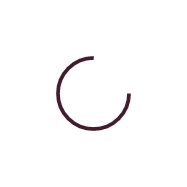
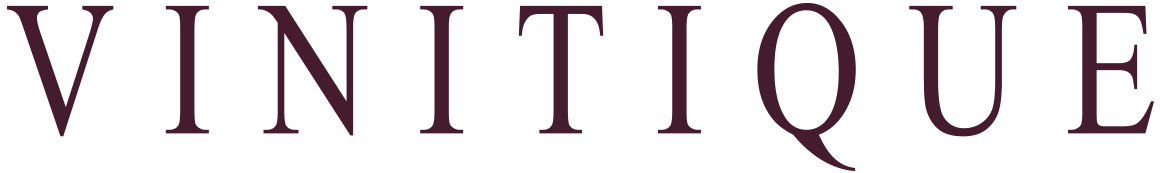
TALK No.02
百々 徹
瀬口:本日は大阪成蹊短期大学教授で、服飾文化について幅広くご研究されている百々 徹先生をゲストにお迎えしております。松濤美術館のダイアン・クライスコレクション展カタログの百々先生の文章が素晴しくて、ずっとお会いしたいと思っていました。今日はzoomですが、お話しできて嬉しく思っております。 百々先生は神戸ファッション美術館に20年ほどいらっしゃって、その時にダイアンさんのレースのコレクションに出会ってアンティークレースの魅力に目覚めたとカタログに書かれていましたが、どういうところに惹かれたのかお聞かせいただけますか。

百々 徹先生
百々:そうですね、私は1993年から2014年までの21年間、神戸ファッション美術館に勤務していました。元々は映像担当として美術館に入ったのですが、ある時、久保速雄さんという日本でも屈指のレースコレクターの方から、自分の持っているアンティークレースの展覧会を開催してくれないかというお話がありまして。たまたま他の学芸員が手いっぱいだったので私が担当することになったのですが、その時はそのレースに関する知識はなくて、単なる白い布ぐらいのイメージしかもっていなかった(笑)。
展覧会担当になったのでライブラリーにあるレースに関する文献を調べてみたのですけれど、写真なのでよく分からない。考えてみたら、収蔵庫にはレースがいっぱい収蔵されているのでそれを見に行けばいいだろうと、ライブラリーの本を携えて収容庫に行ったのです。収蔵目録と照らし合わせて見てみると、これはバンシューだな、これはメッヘレンだな、アランソンレースだなと分かるのですけれど、やっぱり白い布は白い布なんですね(笑)。
本には拡大写真が載っているので、拡大すれば何か分かるのではないかと拡大鏡を持ってきて覗き込んだ時に、今まで単なる白い布だと思っていた目の前のレースと、拡大写真が結びついた。こんなに細かい直角形ができているのか、とか、バンシューレースの特徴的な模様とか、ボビンレースの絡み方によってできてくる模様とか、それらがこの小さな布の中に見えてきた。まるで宇宙が広がるかのように全部留められている。それまでにインドのマハラジャのためにつくられたチェーンステッチなど、細かい手仕事を見る機会はあったのですけれど、それを遥かに超えた「手仕事の宇宙」みたいなものが、せいぜい20センチちょっとで幅が6センチくらいの小さな布の中に詰まっていた。魅力というよりも、ちょっと畏怖に近いものを感じたのが最初ですね。

ボビンレース
瀬口:そうですね、本当に「手仕事の宇宙」! 私もまさにそうだなと思っているのですけれど、服飾文化をずっと学んでこられた百々先生がレースは畏怖の対象とおっしゃるところに感動しました。ところで西洋の服飾史の中ではストールとかレースはどのように位置づけられ、どのような役割を果たしてきたのでしょうか?
百々:難しい質問ですねー(笑)。
例えば古代ローマの元老院に政治家が集まるときには、手拭いのような一枚の布を手に持っていることがステータスだったのですね。原物が残っておらず、いくつか絵の中や文献の中に残っていたりするくらいで、実際にどのようなものだったかはよく分からないのですけれども。重要なのは、寒さをしのぐために身に着けるとかではなく、余剰というか、余分な布を持つということ自体が大きな意味を持っていたということです。装飾品やアクセサリーの本当に重要な役割はそこだと思います。
ファッション美術館の収蔵品に、19世紀初頭のカシミアのストールが一枚あったのですが、カシミアはもともとインドのカシミール地方でつくられていたものですよね。それがなぜヨーロッパに伝わったかというと、実はナポレオンなのですね。ナポレオンが海外遠征へ行った帰りに愛しいジョゼフィーヌのために持って帰った。当時は古代ギリシャの影響もあって、エンパイアスタイルと呼ばれる何の装飾もない真っ白で透けるようなコットンのドレスが流行っていたのですが、そこにカシミアのストールを羽織ったりしたのです。
ファーストレディのジョゼフィーヌが身に着けるようになって、カシミアのストールが上流階級の間で広がっていった。ただ、別にそれがないと暮らしに困るわけでもないし、実用性はないのですね。余剰の布なのです。レースもそうですよね。実用性がないからこそ、そこに特別な意味が宿る。そういうかたちで進化してきたものなのです。

エンパイアスタイル
18世紀の宮廷ファッションの中で、バルブとかラベットと呼ばれますが、女性が髪の毛を結わいて後頭部のところから布を垂らすスタイルがあります。これは長さが決められているのです。貴族には公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵と階級があって、侯爵夫人と伯爵夫人ではバルブの長さが決められている。伯爵夫人なのに長いのを付けていると、あいつ何考えているんだと宮廷の中で後ろ指を差される。そういう階級の中で競い合う、もっと細かいものをつくってやろう、もっとすごいものをつくってやろうと。ぱっと見は全然すごく見えないけれども、それが分かる人にだけ分かるものをつくろうとするわけです。
私がファッション美術館で最初にレースを手にした時には、単なる白い布にしか見えなかったけれど、実はそこにものすごく壮大な手仕事の宇宙が広がっていることに後から気づいた。つまりレースはそれを理解できる人と理解できない人を選別するための道具でもあるのですね。分かる人には分かる、というのは分からない人には分からないということです。あの人はレースの価値が分かっていない、という選別をする役割もあったのではないかと思います。
そしてせめぎあいというか、下のクラスの人たちが上のクラスのマネをして、山を売ったりブドウ畑を売ったりして、次のパーティーまでにレースを仕上げて身に着けてくる、今度は上流階級がその人たちと差別化するためにもっと凝った手仕事を職人たちに求めて、お金をどんと注ぎ込んですごいものをつくらせる。そういうある種イタチごっこのような状態が、1789年のフランス革命直前までのパリの風景、ベルサイユの風景だったと考えていまして、そこに至るまでの間に人間の手仕事の最高峰があったと思うのですね。そのときに、そこまでして装うということに執着し続けた人間の業というか、性というか、エゴというか、なにかすごいものを覗き込んだという気がしました。それがアンティークレースの世界なのだと思っています。
瀬口:面白いです! ストールやレースなどは実用性はないけれど、階級を分けたり差別化したりするときのアイコンとして機能していたわけですね。面白すぎて、ネットに載せるだけじゃ勿体ない。本当に本にして出版したいですね(笑)。
ちょっとヴィニティークに話をつなげさせていただくと、私は最初、ジュエリーのようなストールというイメージでつくっていて、その感覚が「布を持つのがステータス」というお話につながっていたところに、ものすごく感動しました。
わたしはフランスのボルドーにいたのですが、そこから近いスペインのビアリッツにナポレオンがジョゼフィーヌのために建てた美しい建物があって、そこが今ホテルになっていて、好きでよく行っていました。そのジョゼフィーヌがカシミアのストールにつながっていくなど、面白くて今、ちょっと興奮しています。
百々:先ほどお話しした久保速雄さんとのご縁で、レースの展覧会を都合3回やりました。世界レース会議(OIDFA)の日本大会も私が間に入って開催したのですが、その関係でブルーミング中西というハンカチのメーカーさんと出会いました。ブルーミング中西さんはもともと中西儀兵衛商店という明治創業の西洋雑貨商で、やがてハンカチをメインに展開するようになったのですが、例えばスワトウ刺繍 ― 戦前のスワトウ刺繍は今手に入るものでも10万から20万円くらいしますけれど、それとは全く別次元のとんでもないスワトウ刺繍を施したハンカチとか、素晴らしいコレクションをお持ちなのです。そこで2007年に私が「魅惑の正方形」とタイトルを付けて、ブルーニング中西さんのハンカチのコレクション展をファッション美術館で開催しました。
その時に出品されたものですが、19世紀のヨーロッパでは鼻をかむ時にハンカチでかんでいたのですね、ティッシュペーパーが無かったので。その鼻をかむためのハンカチとか、他にもルージュハンカチという、飲み物を飲んだ時にカップについたルージュを拭き取るための赤いハンカチとか、嗅ぎタバコを嗅ぐと茶色い鼻水が出てくるので、それをかむための茶色のハンカチとか、実用のためのハンカチがある一方で、実用性のない、見せびらかすためのレースのハンカチがあったわけです。レースのハンカチを持つことが宝石をはめているのと同じ役割を果たしたのですね。実用性がないからこそ価値のあるものがある、重要なのは、希少価値とか手間暇がかかっていることが装うことの意味に直結して、それ自体が意味を持つ世界というのがかつてあったということです。
まあ、大分これは失われてきているのだけれども、それが本当に失われてしまうと、装うこと自体が非常に平板なものになってしまって、面白味がなくなってしまう。だからこそ服飾文化というものがもっときちんと理解される必要があるのではないかな、と思っていますね。
瀬口:いやー、面白い! いくらでも話が広がっていきますね。ちょっと話が飛びますが、最近、イスラム文化圏の女性がヒシャブの着用を拒む動きが広がる一方で、ヒシャブを活かした着こなしを提案するSNSが話題になったりしています。百々先生はこの動向をどのようにご覧になってますでしょうか。
百々:いわゆる文化というものが平板化していく、フラット化していくと、文化の起伏とか地域差とかが薄まっていきます。でもそれは表裏一体だと思っていて、差異がはっきりしていると排他的であるとか、マイナスの部分もある。先ほどのバルフの長さの話のように、作法というものがついてきますのでね。それと、多くの人たちがファッションというある種のゲームに参加しようとしたならば、ルールはできるだけ単純化してしまう方が、より幅広い層の人々が参加できる。これが今起こっていることだと思うのですね。
やはり人間が装うことを何万年もかけて続けてきて ― その極北の一つが私は18世紀のレースだと思うのですけれども、産業革命が起こって社会が消費社会に移行しフラット化していく中で、別に手間暇かけたものでなくてもいいじゃないか、雰囲気だけレース風のものでもいいじゃないですかという考えが出てくる。子供のころからそういうものしか見ていない子供たちは、とんでもなくすごいものを見分ける力もなくなっていく。
でもそうじゃなくて、かつてはこうだったんだよ、自分たちはどうやってここまでたどり着いて今からどういう方向に向かおうとしているのか、という、人生の座標軸みたいなものを子供たちにもう少ししっかり教えてあげたほうがいいと思うのです。装うことは自分と社会をつなげるまさに「間」のものですから、身近なものから教えてあげるのが大切ではないかな、と。
だからヒジャブにしてもイスラム社会はこうでなければならないと、無理やりやろうとすれば原理主義になってしまいますけれども、原理主義のような極端なやり方ではなくて、なぜヒジャブのようなものが使われて未だに大事にされてきたのか、そういう本質的なところからもう一回考え直していくとことが重要なんじゃないかな、という気がします。
瀬口:そうですね。自分がどこから来て、どの位置にいるのかを知る座標軸って、自分を理解するために必要ですよね。素晴らしいお話をありがとうございました。
河口湖のショップのルメルベイユで、レースのインスタレーションを展示していますので、百々先生にも一度ご覧いただけると嬉しいです。本日は本当にありがとうございました!
(2023年4月11日、オンラインにて)